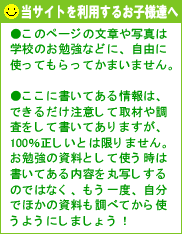|
昔むかし、土佐の国のお侍の家に一人の働き者の奉公娘がおった。
当時は火を大切にして、特に大晦日の晩は絶対に火を絶やしてはならんことになっておったそうな。
ある年の大晦日の晩、家の主人は奉公娘に「火を絶やさぬように」と言いつけて、寝室にさがった。
生真面目な奉公娘は、火を絶やさないように一晩中火の晩をしとったが、年の暮れの疲れが出てこっくりこっくりしておるうちに、ぐっすり寝てしもうた。
一番鶏の鳴き声で、はっと目を覚まして灰をかき混ぜてみたが、火は消えておったそうじゃ。
まだ薄暗い中、奉公娘が途方にくれて外で立ちすくんでおると、誰か向こうから松明(たいまつ)をもってやってくる。
奉公娘は火種をもらおうと、夢中で駆け寄っていった。
すると、松明をもった男は死人を入れる棺おけをかついでおった。
奉公娘が火種を求めると、その男は火種をあげる代わりにしばらくの間棺おけを預かってほしいという。
夜明けまでにはとりに来るというので、奉公娘は承知したそうじゃ。
夜が明ける頃には火も燃えて、奉公娘はほっとしておったが、困ったことに棺おけを取りにくる気配がいっこうにない。
そのうち、主人が起きてきて棺おけが見つかってしもうた。
奉公娘は正直に全てを話し、素直に謝ったそうじゃ。
話を聞いた主人は納得して、奉公娘を許し、棺おけを取りにくるのを待っておったが、いつまでたっても男は現われなんだ。
何か手がかりはないかと、棺おけを開けてみると、驚いたことに、中に死人は入っておらず、大判小判がぎっしりと詰まっておったそうじゃ。
結局そのお金は奉公娘のものになって、その後一生親孝行して暮らしたということじゃ。
|