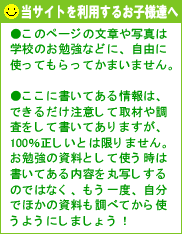|
むかしむかし、室戸の新村にお宮というたいそうきれいな娘がおった。
品も器量もええ娘で、このあたりの若者なら誰もが嫁にするならお宮と思っておったそうじゃ。
ところが当のお宮は、それほどもてはやされても、ひとつも鼻にかけるところがない、素直でやさしい娘じゃったので、ますますお宮を慕う者が増えた。
ついにお寺の若いお坊さんまでがお宮に心を寄せて言い寄ってくる始末じゃった。
これにはお宮も困ってしまい、わざとぼろぼろのきものを着て、顔には墨を塗って過ごすようになったそうな。
しかし、それぐらいのことではお宮の器量をごまかすことはできなんだ。
それどころか、そのいじらしい気持ちがなおいっそうお宮の人気に火をつけてしまったそうじゃ。
そうこうしているうちに、お宮は深く思い悩むようになり、ふさぎこんでいった。
そしてある晩のこと、覚悟をきめたお宮は、家族が寝静まるとこっそり家を抜け出して、荒磯の渕に行った。
お宮はこの村に二度と美人が生まれてこないようにと祈願して、あっという間にその深い渕に身を投げて、みずから若い命を断ってしもうたそうじゃ。
翌日、全てを知った村の人たちは、はじめてお宮の深い心を察し嘆き悲しんだそうじゃ。
それから間もなく、お宮の家の庭石に一本のかずらがからみつき、見たこともない赤い小さな花を咲かせた。
その可憐な姿に村人達はこの花に「お宮が花」と名づけて、お宮を偲び、たいそういとおしんだそうじゃ。
|