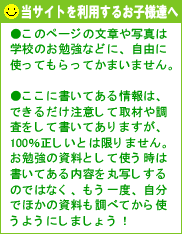|
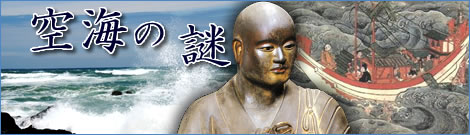
空海についての様々な謎を、初代先達・真魚が突拍子もない発想から 勝手に推測するコーナーです!
もちろん、学術的根拠も一切ありませんので、気楽に、広~い心でお付き合い頂ければ幸いです!
空海の謎のひとつに「語学力」があります。
空海は 遣唐使として福州に辿り着いた時、いきなり流暢な唐語で土地の人達と会話をしたという。
当時の人々からすれば奇跡のような事柄で、それまで無名だった空海が一躍注目を浴びる原因の一つになったとさえいわれています。
いったい、いつどこで空海は語学力を身につけたのか?
空海は、大学時代に正規課程のほかに、唐のなまの現代音を学ぼうと大学の音博士について、すすんで勉強した形跡はあります。
また、奈良の高僧・勤操と親しくしていたことから、当時、海外から帰国した僧や海外からやって来た僧がたくさん出入りしていた大安寺に通っているうちに身につけたのではないかともいわれています。
面白い説としては「空海二度渡唐説」もあります。
遣唐使として唐へ渡る以前に、渤海使節団に紛れ込んで、個人的に唐へ渡ったことがあるのではないか。
その時に、語学を身につけたのではないか、というものです。
空海の年譜の中の「空白の7年」と照らし合わせると、確かにその可能性がないとはいえないでしょう。
さて、上記の事柄に追加して、勝手な私説として「幼少体得説」を提唱いたします!
空海は幼少の頃、既に多くの異国人との交流を持っていて、その時に 語学を体得していたのではないか、という説です!!
空海が幼少を過ごした讃岐国多度郡の近くに、瀬戸内海に突き出した荘内半島という場所があります。
この荘内半島は、その半島にある紫雲出山山頂に古代の高地集落遺跡もあり、邪馬台国に続く第2の大国「投馬国」伝説などがささやかれたりもする場所です。
「投馬国」伝説の真偽はここでは割愛させて頂きますが、地理的に見て、この荘内半島に古代から多くの国内外の船が出入りしていたのは確かなようです。
この半島には 関の浦という場所があります。
鎌倉・室町時代には沖を航行する船舶から通行税を徴収して、山口県の上関、中関、下関と並んで、四大関所と呼ばれていました。
菅原道真や藤原純之、小野好古等の歴史的人物もこの関の浦を訪ねたといわれています。
また、半島最高峰である紫雲出山山頂からは瀬戸内海を航行する船が全てチェックできます。
日本国内ならず、海外から畿内へ向かう船のほとんどがここを航行していたことから考えると、この半島には当時、かなりの数の異国人が出入りしていたと考えられないでしょうか?
半島には今もなお、中国語で書かれた墓らしきものが残っているという話を地元住人から聞いたこともあります。
また、異国へ行って戻ってきた人物をモチーフにしたといわれる浦島太郎伝説の郷でもあります。
空海は幼少の頃、この半島へ出かけては異国人と出会い、たわいもない会話を楽しんでいた。
また、半島に下り立った異国人が幼少の空海が過ごしていた地域まで足を運んだ際、その人達と交流しているうちに語学を身につけていった。
「幼少体得説」いかがでしょうか?
いずれにせよ、空海自身に生まれ持った特異な語学の才があったことが一番の理由だったような気がします。
空海はやっぱり天才ですネ!!
|