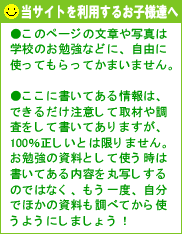|

【第3回】讃岐におけるうどんの歴史と讃岐うどんの可能性を拡げる「新メニュー」のご紹介
今回は讃岐におけるうどんの歴史概略と、讃岐うどんの新しい可能性を拡げる力を秘めた讃岐うどんの新メニューをご紹介。
| 弥生時代 |
そば(種子)伝来 |
| 古墳時代 |
小麦・大麦伝来 |
| 飛鳥・奈良時代 |
香川県下で小麦栽培開始
索餅(さくべい)伝来 |
| 平安時代 |
香川県下で水車登場
こんとん(菓子・うどんの先祖)伝来 |
| 鎌倉時代 |
索麺(そうめん)伝来
挽き臼伝来 |
| 室町時代 |
そうめん座(同業組合)設立
ひやむぎ登場
線状形うどん登場(現在のうどんの原形) |
| 安土・桃山時代 |
小豆島で手延べそうめん製造
そば登場 |
| 江戸時代 |
讃岐うどん登場
香川県下で水車製粉開始
香川県下でうどん屋開業
讃岐藩主そうめんの生産を奨励 |
| 明治 |
金毘羅小麦栽培
パスタ伝来
香川県下で製麺機普及 |
| 大正 |
中華そば登場
香川県下でひやむぎ製造(大正6年) |
| 昭和 |
即席麺登場(昭和33年)
ゆでうどんのポリエチレン袋包装開始(昭和30年代後半)
讃岐うどんの専門店化・大型化(昭和40年ごろ)
生麺・半生麺の製造開始
セルフサービスのうどん店登場
冷凍うどんの本格製造
讃岐うどん品評会(農林水産大臣賞)開始(昭和54年)
香川県下のうどん製造量が全国1位(昭和63年~) |
| 平成 |
国民文化祭「うどんフェア」開催(平成9年)
世界麺フェスタ開催(平成20年) |
※綾川町うどん会館のうどん資料パネルより
上記の表は、讃岐うどん発祥の地ともいわれる香川県綾川町にあるうどん会館の展示資料ですが、やはり通説では線状形うどんの登場は室町時代となっており、空海が「讃岐うどんの切り麺技術を中国から持ち帰って讃岐に広めた」という伝承を実証するには麺棒などの普及時期とのギャップがネックとなってしまうようです。
この点については、引き続き調査を続行します。
さて、つい最近、丸亀の讃岐うどん屋「寿美屋」さんで、讃岐うどんの可能性を広げる新メニューを見つけました。


「すいどんくん」というメニューです。
まだ地元情報誌でも紹介されていない本邦初公開のメニューと思われます。
線状に切る前の讃岐うどんをゆでて、具材を包み込んだもので、平日午後1時以降限定5食のメニューです。
具材は讃岐コーチン、豚肉、シーフードから選べます。
イタリアのパスタ料理を思わせるのですが、食感はパスタではなく、あきらかに讃岐うどんのそれ。
讃岐うどんの歴史からすれば、切り麺以前に先祖返りしたものを、現代風にアレンジしたメニューとも言えるかも。
従来の讃岐うどんと比較するというよりは、この「すいどんくん」の発想を使えばイタリアのパスタ料理をはじめ、世界のあらゆる料理に利用できる「新しい食材としての讃岐うどん」という可能性が見えてくるようで私はとても嬉しくなりました!
機会があれば、ぜひ皆さんにもご賞味頂きたい逸品ですね。
【第4回】世界麺フェスタ
|